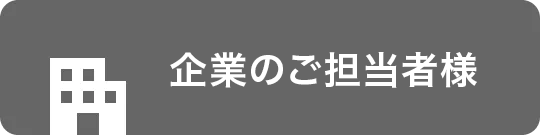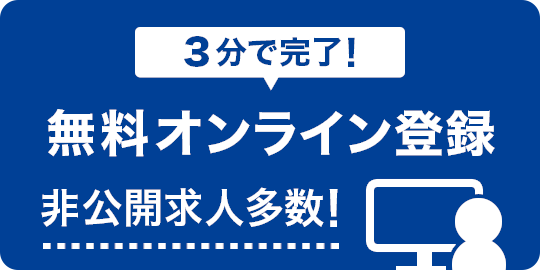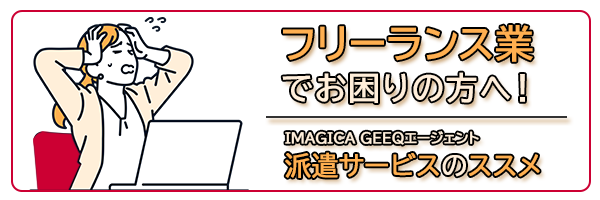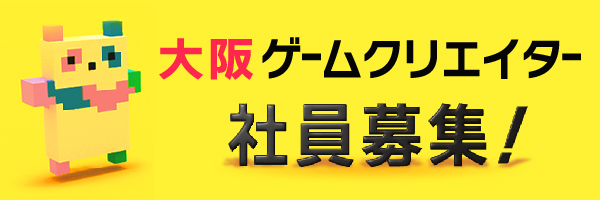【前編】『Hi-Fi Rush』開発陣が明かす、Tango Gameworks独自のクリエイティブ文化
2025/11/07
【前編】『Hi-Fi Rush』開発陣が明かす、Tango Gameworks独自のクリエイティブ文化
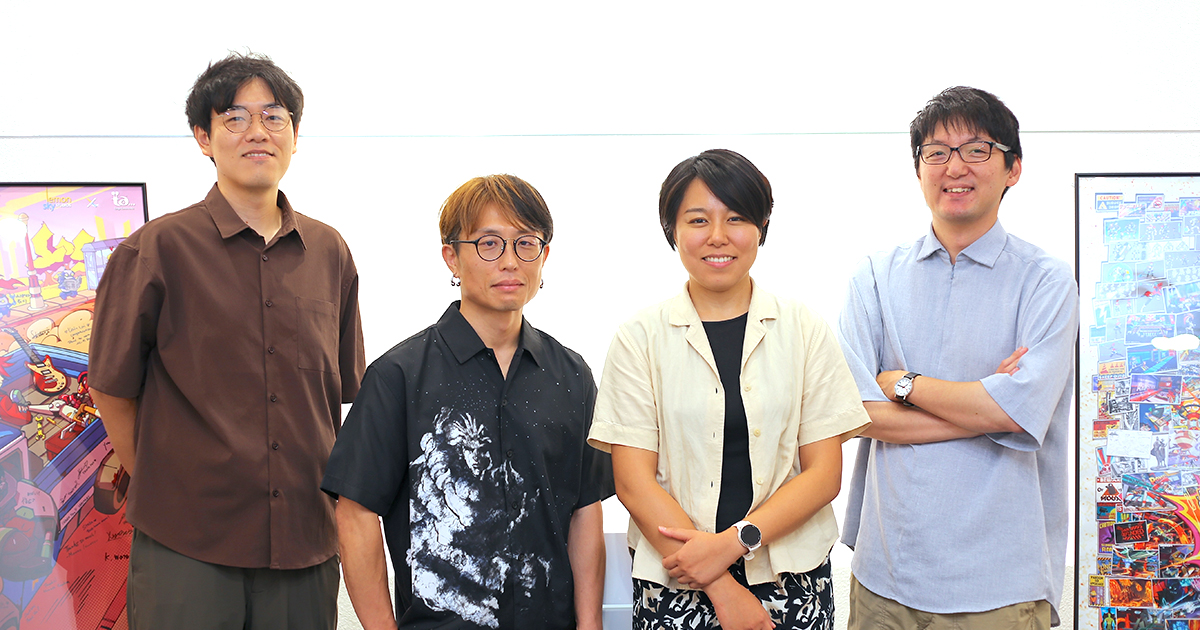
「The Game Awards 2023」でベストオーディオデザイン賞を受賞するなど、世界的に高い評価を獲得したリズムアクションゲーム『Hi-Fi Rush』。その開発を手がけたTango Gameworksは、2024年よりKRAFTON新体制のもと、新たなスタートを切りました。
今回は『Hi-Fi Rush』の開発に携わった同社の中核メンバー4名に、同作を振り返りながらTango Gameworksならではの開発スタイルや、ユニークな社風がどのように受け継がれているのかについてお聞きしました。
今回は『Hi-Fi Rush』の開発に携わった同社の中核メンバー4名に、同作を振り返りながらTango Gameworksならではの開発スタイルや、ユニークな社風がどのように受け継がれているのかについてお聞きしました。
なぜ個性豊かな4人のクリエイターはTango Gameworksに集ったのか
ーー今日は「Tango Gameworksらしいゲーム制作とは?」をテーマにお話をお聞きできればと思います。まずは皆さんの自己紹介をお願いします。
山崎:プログラミングチームリーダーを務める山崎と申します。Tango Gameworksの全ての作品にシステムプログラマーとして携わっています。業界歴は20年で、Tango Gameworksには11年前に入社しました。
私はこれまでコンシューマー業界で長く働いていましたが、ある時「新たなタイトルを、完全にゼロから作ることに挑戦したい」と考え、Tango Gameworksに知人の紹介で飛び込むことになりました。
私はこれまでコンシューマー業界で長く働いていましたが、ある時「新たなタイトルを、完全にゼロから作ることに挑戦したい」と考え、Tango Gameworksに知人の紹介で飛び込むことになりました。

村岡:UIチームリードの村岡です。キャリアのスタートはソーシャルゲーム系の2Dデザイナーでした。Tango Gameworksに入社したのは2019年4月で、今年で6年目になります。
私もTango Gameworksは知人の紹介で知りましたが、実はホラーゲームが苦手で……。面接で「私はホラーゲームが苦手ですが、それでも大丈夫ですか?」と質問したんですよ。そこで「大丈夫じゃないかな」と回答をいただいて、ホラーゲーム未経験ながらこの会社に入社し、『Hi-Fi Rush』では初めてのUIリードデザイナーを経験させていただきました。
私もTango Gameworksは知人の紹介で知りましたが、実はホラーゲームが苦手で……。面接で「私はホラーゲームが苦手ですが、それでも大丈夫ですか?」と質問したんですよ。そこで「大丈夫じゃないかな」と回答をいただいて、ホラーゲーム未経験ながらこの会社に入社し、『Hi-Fi Rush』では初めてのUIリードデザイナーを経験させていただきました。

石川:キャラクターアートチームリーダーの石川です。業界歴は17年で、最初は映像系の会社で宣伝PVや遊技機系の映像制作をやっていました。転職のきっかけは、Tango Gameworks設立当時「東京に新しいゲーム会社が立ち上がり、優秀なメンバーが参加しているらしい」と噂を聞いたから。
あの頃はまだ、独立したクリエイター自身が会社を立ち上げるというムーブ自体に物珍しさがありました。受託ではなく自分の手で作品を作りたいという想いがあったことから、この会社に入社を決めました。その後はサバイバルホラーゲームシリーズのエネミーや『Hi-Fi Rush』のモデル全般を担当してきました。
あの頃はまだ、独立したクリエイター自身が会社を立ち上げるというムーブ自体に物珍しさがありました。受託ではなく自分の手で作品を作りたいという想いがあったことから、この会社に入社を決めました。その後はサバイバルホラーゲームシリーズのエネミーや『Hi-Fi Rush』のモデル全般を担当してきました。

畠山:アニメーターチームのリーダーの畠山です。実は私も知人経由でTango Gameworksを知った人間です。設立当時、新しいスタジオとしてインタビュー記事が掲載されていたのを見て興味を持ちました。
私は『VANQUISH』(プラチナゲームズ開発/セガ発売のTPS。Tango Gameworks前身の創業者がディレクターを務めていた)にハマっていて、当時のインタビューでもこのタイトルに言及があったんです。「こんなアクションゲームを作りたい!」と思って入社しました。
私は『VANQUISH』(プラチナゲームズ開発/セガ発売のTPS。Tango Gameworks前身の創業者がディレクターを務めていた)にハマっていて、当時のインタビューでもこのタイトルに言及があったんです。「こんなアクションゲームを作りたい!」と思って入社しました。

ーー石川さんと畠山さんはほぼ初期メンバーですよね。それこそ現在KRAFTON体制になる以前の空気感も知っていると思いますが、これまでの体制変更(※)について、率直に現場はどう感じていましたか?
※ 創業の約半年後、2010年10月28日付で米ゼニマックス・メディアにより買収され、同グループ内の開発スタジオとしての活動がスタート。2024年5月に突如スタジオ閉鎖が発表されたが、韓国のKRAFTONが事業を継承し、現在に至っている
石川:入社したタイミングでゼニマックス・メディアの買収があり、会社名がTangoからTango Gameworksに変わったんですよね。ただ、そういった動きがあることは知りつつも、クリエイターとしての開発方針や現場の空気は基本的には全く変わっていませんでした。
畠山:開発現場でディレクターとして立つ人間も、創業時からのポリシーのもとで育ってきた経緯があります。例えば「作品を良くするために、自由にみんなの意見を取り入れたい」というスタイルは、今もTango Gameworksのものとして強く周知徹底されています。KRAFTON体制として改めてスタートを切ることができた今も、そこは変わりません。
Tango Gameworksらしさとはなにか
ーー「作品を良くするために、みんなの意見を取り込む」という姿勢は誰のものでもなく、Tango Gameworksに通底する思想であるとのことですが、ワークフローや開発スタイルに特有の開発文化や空気感などが表れる具体的なエピソードはありますか?
村岡:UIチームは以前、仕様書がなかったんです。私は仕様書でガチガチに固められたソーシャルゲーム開発現場から来ているので、入社直後は広大な牧場に放牧された気分でした。
何はともあれモックを作って「これ、どう?」と企画チームやディレクターに見せて、そこから議論を始める、といったことも珍しくありません。もちろん仕様が完全に固定化された環境でも創意工夫はできますが、Tango Gameworksでは完全な自由を得たデザイナーならではのクリエイティブが出せるので気に入っています。
何はともあれモックを作って「これ、どう?」と企画チームやディレクターに見せて、そこから議論を始める、といったことも珍しくありません。もちろん仕様が完全に固定化された環境でも創意工夫はできますが、Tango Gameworksでは完全な自由を得たデザイナーならではのクリエイティブが出せるので気に入っています。
畠山:村岡の話はあくまでUI限定で、もちろん全体の仕様書がないわけではありませんよ。バトル等は土台となるような仕様書はあります。以前は仕様書が少なかったのは事実ですが、今は仕様に目を通して相互理解し合う文化も育ってきています。
肝心なのは仕様書通りに作れば上手くいくというものではないこと。特に、カットシーンではないインゲームイベントなどは、ディレクターの意図やニュアンスを汲み取って、アニメーター自身がほぼ全ての裁量を持って自由に作ることが多いです。
むしろクリエイター側から「ここに説明が足りないと思うので、イベントシーンを入れても良いですか?」とディレクターに聞きにいくこともあります。かなりフラットな関係性でゲーム制作をしていますね。

山崎:私は開発環境を整えたり、ツールを作ったりするシステム側の人間ですから、半歩下がって皆さんの活躍を見ている立場ですが、いつも誰かが立ち話をしていて、どんどんゲーム内容がブラッシュアップされていくんです。
たまにプレイすると仕様が変わっていて、それに伴ってパフォーマンスも落ちているので、私は「みんながやりたいことを実現できる環境」を作っていく。例えば、以前あったプロジェクトでは「空を飛ぶ仕様」が急に出てきたんです。あれはすごく負荷が高かったのですが、絶対に面白くなるので、みんなで頑張って実現しました。
たまにプレイすると仕様が変わっていて、それに伴ってパフォーマンスも落ちているので、私は「みんながやりたいことを実現できる環境」を作っていく。例えば、以前あったプロジェクトでは「空を飛ぶ仕様」が急に出てきたんです。あれはすごく負荷が高かったのですが、絶対に面白くなるので、みんなで頑張って実現しました。
ーー「言ったからにはクオリティを出そう」とクリエイター自身が頑張って、山崎さんが技術的に実現する。すごくダイナミックにゲームが組み上がっていく感じがしますね。皆さんはデスク自体も近いんですか?
村岡:セクションごとにデスクがありますが、執務室内に休憩スペースがあって、そこでコーヒーを飲んでいたら誰かが寄ってくるという感じです。小休憩しながら開発の話をすることも多いですね。
山崎:気を遣って「申し訳ないけど時間をください」とお願いするのではなく、ふらっと意見を言える関係性だし、物理的な近さもあります。ディレクターも近くにいるので、その意味ではコミュニケーションは活発だと思います。
『Hi-Fi Rush』思い出トーク。ディレクターさえ知らないアイデアが盛りだくさん
ーー皆さんはそれぞれ入社時期が異なりますが、全員『Hi-Fi Rush』に関わっていたと聞いています。これまでに語られた「誰でもアイデアを入れ込める」「フラットな関係性」などの特徴を表すエピソードがあれば教えてください。

畠山:『Hi-Fi Rush』は、大きなプロジェクトの開発が終わったあと、ディレクター(ジョン・ジョハナス氏)とプログラマーだけでプロトタイプ制作を始めていたと記憶しています。「あそこ、何やってるんだろうね?」とよく話題になっていましたね。
その後、サウンドプログラマー含むサウンドチームのメンバーや、アニメーターの私も参加し、アクションの検証などを含めたゲームの中身の試行錯誤をずっとやっていました。その後にモデラーやエフェクトが合流して、各チームからも1,2名の応援が来て、少しずつ開発規模が大きくなっていきました。
その後、サウンドプログラマー含むサウンドチームのメンバーや、アニメーターの私も参加し、アクションの検証などを含めたゲームの中身の試行錯誤をずっとやっていました。その後にモデラーやエフェクトが合流して、各チームからも1,2名の応援が来て、少しずつ開発規模が大きくなっていきました。
山崎:その当時、Tango Gameworksでは内製エンジンが使われていたんです。しかし、本作はUE4で開発されていることから、ディレクター自身がブループリントを自分で組んで遊びの設計をしたり、UI設計をしたり、ボイスまで自分で入れて作り込んでいました。ディレクターも自分で手を動かしたいタイプだったので、「UE4なら(プログラマーになにかをお願いしなくても)自分でゲームを作れる!」と喜んで作業をしていましたね。
石川:私はモデラーとして初期の頃から関わっていましたが、これまでの8年間グロテスクなオブジェクトをずっと作っていたので、急にトゥーンシェーディングをやり始めるということになって驚きました。そこから2,3ヶ月くらいセルルック調の絵作りを勉強しましたが、あれは楽しかったです。

山崎:私は「ついに2ラインが本格的に動き始めた」という状況を受け、ライン稼働が維持できる環境の構築に勤しんでいました。コロナ禍もありましたので、あの時期は個人的にかなり大変だった記憶があります。リモート対応のための仕組みづくりなども率先して行っていました。
ーーたしかに、時系列を考えると、『Hi-Fi Rush』は他タイトルと2ラインだったわけですね。独自の魅力を持つ、ちょっと変わったタイトルだと思いますが、皆さんプロジェクトに入ったときの印象はいかがでしたか?
石川:プロトタイプ時点でかなり面白かったんですよ。「これは面白いゲームが作れるな!」と感じました。
畠山:私はアニメーターとしてアクションゲームを作りたい願望が結構あったんですよ。これまではホラーゲームを中心に作ってきた中で、もちろんホラーはホラーならではの「どうすれば怖く見せられるか?」という楽しみはあったのですが、やはりアニメーターとしては「カッコイイもの」を作りたいという意思が昔からありました。本作はまさに、その思想と作品自体の特性が合致していましたね。

村岡:私も直前のプロジェクトが超常的な内容だったので、頭の切り替えが大変でした。
ちなみに私がタスクを頂いたタイミングは、すでにワンステージのボスまで倒せるところまで進んでいました。個人的には、この時点で「スムーズに進行できてるプロジェクトなんだな」とは思いましたね。
ちなみに私がタスクを頂いたタイミングは、すでにワンステージのボスまで倒せるところまで進んでいました。個人的には、この時点で「スムーズに進行できてるプロジェクトなんだな」とは思いましたね。

-
 To Creator編集部
To Creator編集部 -
Tips/ノウハウ、キャリアに関する情報/最前線で働く方へのインタビュー記事など、クリエイターの毎日に役立つコンテンツをお届けしていきます!